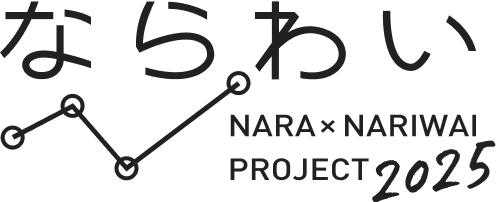プロジェクトの概要
奈良の伝統的工芸品である「奈良晒」を製造する株式会社岡井麻布商店。150年以上の歴史を持ちながら、近年では積極的に外部人材の採用にも取り組んでいます。ここで、6代目・岡井大祐さんとともに、「麻のあるライフスタイル」をテーマとした商品(モノ・サービス)を考えていくプロジェクトです。
参加者のみなさんに期待すること:「専門スキルは、ないほうがおもしろいんちゃいます?好奇心のある方と、横並びで一緒に考えていきたいです!」
参加者のみなさんに持ち帰ってほしいこと:「『おもしろそう』と感じたら、『よし来いっ、飛び込んで!!!』って感じです(笑)。いただいた提案から試作を重ね、商品化につながる可能性もあります!」
かつて奈良は、高級麻織物の一大産地でした。
室町時代にはすでにその原型があり、江戸時代に一大産業へと成長した高級麻織物を「奈良晒(ならさらし)」といいます。
徳川幕府の御用達品として、武士のフォーマルウェア「裃(かみしも)」や、茶道に欠かせない布「茶巾(ちゃきん)」となり、文化を担いました。

その製造工程は合計で10以上にも及びます。大きく3つにわけると、麻の繊維から糸をつくる「苧うみ(おうみ)」、糸を織る「織布(しょくふ)」、不純物を取りのぞき、白く仕上げる「晒(さらし)」。
そうして生み出される優しい風合いの奈良晒を、身近に感じられる空間が奈良市にあります。

BONCHIから、目と鼻の距離にある「麻布おかい 奈良店」です。猿沢池や五重塔からも近く、観光客も多く訪れる株式会社岡井麻布(おかい まふ)商店の店舗です。
「こんな会社です」
ここで迎えてくれたのは、6代目・岡井 大祐(おかい だいすけ)さん。

写真の笑顔のとおり、気さくな印象の大祐さんが、岡井麻布商店の歴史を紹介してくれました。
「岡井麻布商店の創業は、江戸末期の1863年です。明治、大正、昭和へと時代が進むにつれ、綿が生地の主流となり、本社のある奈良市田原地区の奈良晒の織元(おりもと)がどんどん廃業していきました。とうとう、うちが地区で最後の一軒となった時、おじいちゃん(4代目)が『細くでも、奈良晒を長く続けていこう』と決意して、今があります」
続く5代目・孝憲(たかのり)さんは、奈良晒の自社製品の販売を展開。大手百貨店での卸売を開始しました。
その後、2003年に路面店第一号となる「麻布おかい 東向(ひがしむき)店」を出店。2010年にはこの「奈良店」がオープンしました。
このように、奈良晒の織元という川上から、自社製品の販売という川下へ事業展開した経緯を、大祐さんはこう話します。
「麻をいろんな方につかってほしい。織元としてものづくりを続けるだけでなく、現代になじむ『麻のあるライフスタイル』を提案していくことにしたんです」

「提案」の幅は広い。奈良店の店内にはのれん、扇子といった定番商品から、日傘、クッションカバー、マスク、キャップ……と、さまざまな手織麻の製品が並んでいる。
おどろくことに、これらの商品は、生地づくりから商品企画までを自社で手がけているという。
「ぼくらが提案したいのは『麻のあるライフスタイル』です。日々自分たちで麻を織ってつかって。暮らしの気づきを大切にしながら、商品開発にも取り組んできました」
「取り組みたいプロジェクト」
岡井麻布商店がならわいに参加したのは、次のような思いからだという。
「ぼくは、この仕事について20年近くになります。経験を重ねた反面、どうしても盲目的になったり、視点が偏ってしまうところもあると思います。そんな今だからこそ、参加者のみなさんの自由で新鮮な視点を楽しみにしています」
今回は、参加者のみなさんとともに、あらたな商品(モノ・サービス)を考えたいという。
商品については、二つの方向性が考えられそう。
一つは、「麻のあるライフスタイル」をテーマとしたモノの開発。ライフスタイルといっても、家にこだわることなく、「オフィスにどんなモノがあったらよいだろう」「コワーキングスペースでは」「カフェでは……」と柔軟な思考にヒントがありそうです。
もう一つは、麻を用いたサービスの提供。ひょっとしたら、「麻のサブスクリプション」なども考えられるかもしれません。
ここで紹介したいのは、岡井麻布商店で新商品が生まれるプロセスです。
糸口となるのは、6代目・大祐さんが2018年に立ち上げたブランド。
「麻本来の魅力を素のままに伝える」というコンセプトの「Mafu a Mano(マフ ア マノ)」です。

それまで、岡井麻布商店では手織麻生地を染色した商品も多くみられました。
「手織の麻生地は、染色にも適しています。機械織の麻と違い、撚糸(ねんし)を行わないため糸にねじれがなく、きれいに色が染まるんです」
しかし、あるとき大祐さんは、染色により付加価値を高めるのではなく、「きなり」と呼ばれる横糸そのものの自然な色合いこそが価値だと気づいた。
「ぼくにとって、『きなり』は当たり前すぎたんです。子どもの頃から、工房でおばあちゃんが糸をつくるのを見て育ちましたから。今改めて横糸を見るといいですね。つくり手によっても糸の仕上がりが変わる。糸から個性が見えるんですよ」
「Mafu a Mano」のラインナップの中でも、大祐さんが手応えを感じたのは、2020年に商品化されたコーヒーフィルター。

手織麻生地のコーヒーフィルターを考案したきっかけは、麻袋でコーヒーの生豆を運ぶことにある。
「手織の生地でコーヒーフィルターをつくったら、どうなるんだろう?」
小さな疑問を調べてみると、手織の麻でつくられたコーヒーフィルターは、ほとんど販売されていないことがわかった。
「おもしろそうだな、つくってみよう」
大祐さんは、亜麻(linen)、大麻(hemp)、苧麻(ramie)と複数の麻を組み合わせ、コーヒー本来の味を引き出せるよう、生地の密度を調整。10種類の試作を経て、商品化に至った。
ここで大祐さん。
「『わくわくするね』『おもしろそう』。それが、商品開発するときの合言葉なんです」
「こんな関わり方を考えています」
ー今回、ならわいの参加者のみなさんに期待するスキルはありますか?
「ない方がおもしろいんちゃいます??ぼくらはデザインやマーケティングの専門家にアドバイスを受けたいわけではないんですよ」
「それよりも、記事を読んで『岡井麻布おもしろそう』と感じてくれる人がいたら、『よし来いっ!!!』って感じです(笑)。ホント、飛び込んでみて。まずは麻の生地を見て、触れて、『こんなんあったら楽しそうじゃない?』と横並びで話したいです」

ならわい第1回目である10/16の現地訪問時には、BONCHIと奈良店をベースキャンプにして、色々な可能性を模索してください。希望する方は、麻を織ることもできます。ぜひチャレンジしてみてくださいね。
「参加を考えるみなさんへ」
最後にあらためて、大祐さんに奈良晒の魅力についてうかがう。
すると、意外な返事がかえってきました。
「奈良晒って、ときにちょっと不便なんです」
「『ちょっと不便』は、裏返せば『暮らしの豊かさ』にもつながります。たとえば、紙のコーヒーフィルターだったら、使い捨てができて楽ですよね。でも、手織ならではの質感や、使うたびにコーヒー色に染まっていく風合いは、やがて愛着へと変わります」
「BONCHIの目線」
BONCHIの4階にあるコワーキングスペースでは、岡井麻布商店の蚊帳生地をカーテンとして使用しています。蚊帳生地を透過した柔らかい光は心地よくて、良いアイデアが生まれそうな予感がします。

岡井麻布商店は150年以上にわたって、奈良晒の伝統を受け継いでいます。その秘訣は、時代に合わせて変化していく風通しのよさであるように感じました。
6代目・大祐さんは、「やってみなはれ」と背中を押してくれる人だと思います。肩ひじはらず、ぜひ一緒に麻の未来を考えてみませんか。
(2022/7/14訪問)